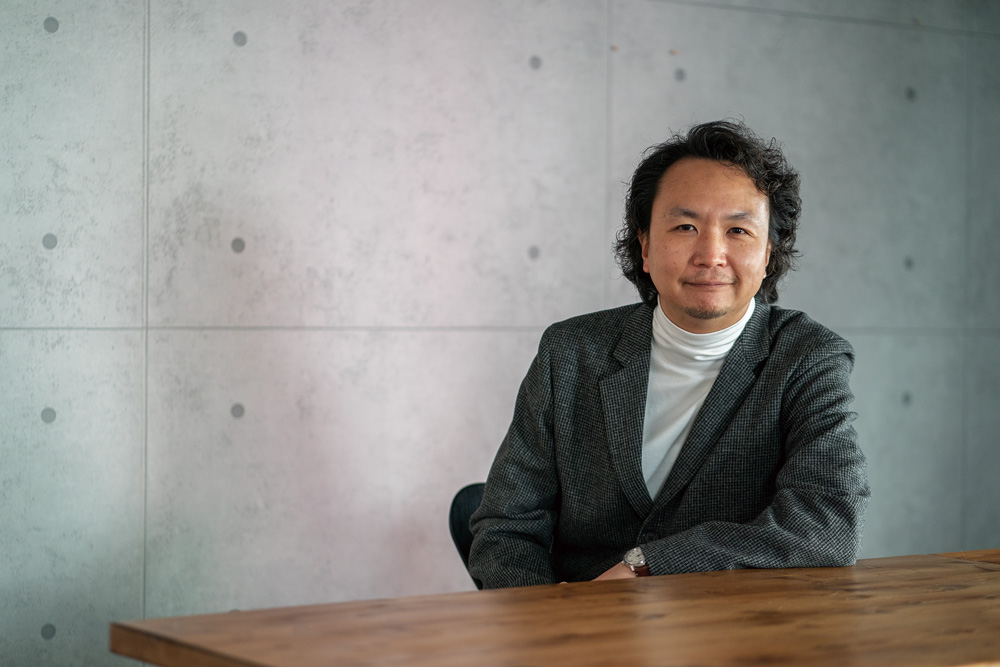KAATで白井晃・前芸術監督時代から芸術参与として関わり(2019年4月~2021年3月)、コロナ禍の2021年4月、芸術監督に就任した長塚圭史。2021年度の年間プログラムにシーズン制を導入し、一年目のシーズンタイトルを「冒」(※1)と名づけ、「劇場をひらく」ことに注力しました。様々な制約から、その実現も容易ではなかった一年。考えていたことやチャレンジしたことをふりかえります。
聞き手・文 : 編集部 写真 : 加藤 甫
―芸術参与の期間からコロナ禍をはさんで芸術監督になり、KAATでやろうと考えていたことに変化はありましたか?
僕が芸術監督の仕事を具体的に意識しはじめるようになったのは、ちょうどコロナ禍が始まった頃、2020年の春頃でした。一年後の船出を考え、具体的にプログラムを組みはじめ、劇場が新型コロナで閉館を余儀なくされた時期だからです。その頃、国からのイベント自粛要請に対して演劇関係者が発言をするたびに、ネット上で大きな物議をかもすといった状況がありました。日本では、演劇を必要としているのはごくごくわずかな演劇好きの人たちで、文化としてはほとんど認められていない可能性が高いのだと、その時にあらためて感じて。演劇関係者が何か口にするたびに「違う」と言われるのは悔しかった。「この状況をどうにかしたい」という熱が、僕のなかでも生まれました。
2020年度の始まりは新型コロナの影響により、劇場内外の人と会って話をする時間がほとんどありませんでした。劇場内でも僕が思い描いていたコミュニケーションが遮断されてしまったことは想定外でしたね。必然的に自分で考えなければならない時間が増えました。
参与の時には、物理的な場として劇場に「来てもらう」こと、劇場がどうあるべきかを意識していたと思います。ですがコロナ禍を経験してからは、演劇や舞台芸術について人々がどのように考えているかという、より本質的な問いにフォーカスが移っていったといえるかもしれません。演劇が文化としてまだ認められていないと感じたのであれば、どのようにひらき伝えていけばよいか。未曾有の事態は、僕がKAATという公共劇場において何をしなければならないのかを深く考えるきっかけになりました。
―2020年2月以降、公演の中止や延期、収容人数を制限しての上演、上演する際の徹底した感染対策など、様々な困難を経験しました。そんななか、舞台表現の可能性についてはどう感じていましたか?
目の前にお客様がいて、初めて演劇という表現が成立することを、これほどまでに強く認識させられたことはありませんでした。当たり前のことではありますが、お客様は僕らが演技をする対象となる人たちです。2020年6月に下北沢のザ・スズナリで上演を予定していた新ロイヤル大衆舎の公演(※2)が、4月の緊急事態宣言によって中止になりました。何かしようと、毎日違う作品のリーディングを配信することになった時に、そのことを痛感したんです。公演の稽古は、物理的に会うことができる状況ではなかったので、LINEのグループで音声通話を利用して行いました。ですが稽古をすればするほど、お客様のいない映像配信という表現に「これでいけるのかな」というもやもやとした不安を抱えていきました。そんなある日、小劇場の感染症対策ガイドラインにもとづいて、お客様も30人前後入れられるかもしれないと聞いた時、僕らの表情がガラッと変わって。それを待っていたんですね。配信は、劇場には足を運べない人たちと出会うことができる、新たにひらかれた有意義な方法です。でも配信の向こう側にいるお客様の反応をつかみとることは困難です。やはりたとえ半数だったとしても、お客様がそこにいることの力、その価値の大きさをあらためて実感することになりました。劇場は、出演者やスタッフとお客様、そこに居合わせた人たちの関係性が生まれる場であり、特別な体験ができる場所なのです。
―芸術監督に就任してから一貫して取り組んだ「劇場をひらく」ことについて、お考えを聞かせてください。
繰り返しになりますが、コロナ禍で切実に思ったのが、演劇の魅力を知っている人がどれだけいるのだろうかということでした。より多くの人たちに、劇場での特別な体験、劇場で起きるマジックを知ってほしい。あなたがいなければ、このマジックは起きないのです。そのためにはすでに演劇の魅力を知っている方々以外へも、扉をひらいていかなければなりません。そこで劇場のなかだけで完結しないように、時間がかかったとしても様々な場所に出かけていき、いろいろな人に出会っていくことが、極めて地道ながらも一つのやり方になるのではないかと考えました。それが「冒」メインシーズンのラストを飾る「KAATカナガワ・ツアー・プロジェクト」として、かたちになっています。
また劇場の新たな広報誌として、季刊誌『KAAT PAPER』を創刊したのも一つの挑戦です。芸術監督が考えていることや、劇場がある地域のこと、お客様の声など、ひらかれた誌面づくりを目指しました。『KAAT PAPER』に限らず、劇場とはどういう場所なのかということをいかにして伝えていくかということは、引き続き考えていく必要がありますね。
もちろん、芸術性の高い作品をつくっていくことも続けています。プログラムを考える時には、「閉じていないか? ひらいていく力はそこにあるか?」という視点でしっかりと精査をしました。

作 : 北條秀司 構成台本+演出 : 長塚圭史 写真 : 細野晋司
―「KAATカナガワ・ツアー・プロジェクト」はどのような企画ですか?
僕が芸術監督就任後、初めて書き下ろした新作『冒険者たち~JOURNEY TO THE WEST~』(※4)が、KAATを皮切りに、川崎、相模原、大和、厚木、小田原、横須賀と県内6都市をめぐるプロジェクトです(※5)。
このプロジェクトは5年で3回行うことを目指しています。一年目はまずは各地に赴く。そこで新たなお客様と出会い、演劇の魅力を伝えていきます。回を重ねるごとに、公演会場をどんどん増やしていくことができればいいのですが……そのぐらいの気持ちで取り組んでいます。各地の劇場、お客様との関係性をどのようにつくっていくかということについては僕も悩みながら、まずは一回やってみて、試行錯誤しながら継続していきたいですね。
今回は自分も劇作家として神奈川県のことを勉強しながら、昔話や言い伝えを物語に反映しました。劇作をするプロセスのなかで、県内の様々な場所を訪れ、まちを知ることができるのも面白い。
またこのプロジェクトが、各地の公共劇場とどのように共同製作ができるかを考える足がかりになればとも思っています。県内にとどまらず、ゆくゆくは国内各地の劇場と、発想やクリエイションがつながり合うような交流がもてるようになるといいですね。

―新型コロナの影響があったなか、新聞や雑誌における演劇ジャンルの一年をふりかえる記事では、KAATの公演が取り上げられることが多い年になりました。
とても多くの媒体で取り上げていただいています。たぶん今の社会と、KAATでのチャレンジが合致したからではないでしょうか。この状況下では各地の劇場が、挑戦的な企画に取り組むことはなかなか難しかったと思います。そんななか、図らずもKAATは芸術監督の交代という節目、変化を求められる時期を迎えることになりました。そして劇場を「ひらく」方針をさらに推し進めることになった。僕が芸術監督になるタイミングがコロナ禍だったことは、まあ受け入れるほかありませんでしたから。これまでにやったことのない立場ですから、何とも比べられませんが、やれることをコツコツと、時に大胆に積み重ねていければと思います。
※1
春から夏をプレシーズン(6プログラム)、秋からをメインシーズン(10プログラム)と位置づけ、劇場に季節感とリズムを取り入れた。「冒」という言葉は「飛び出す、はみ出す、突き進む」という意味をもつ。未知なる世界へと踏み出す勇気と、既成概念を打ち壊す芸術の原点というコンセプトが込められている。
※2
森本薫作『無法松の一生~富島松五郎傳~』、岸田國士作『麺麭屋文六の思案』『遂に「知らん」の文六』の同時上演(構成台本+演出 : 長塚圭史)が中止となった。この時に『緊急事態軽演劇八夜』と銘打ち、読み語り芝居を動画配信。東京都内の小劇場における新型コロナウイルス感染症対策ガイドラインにもとづき、35席ほどの観客席を販売した。
※3
初演は2017年。KAATでは劇場1階のアトリウムに設営した特設劇場にて上演。劇場そのものを、大通りから丸見えのアトリウムに引っ張り出して挑んだ“大衆演劇”となった。
※4
『西遊記』を原作とした戯曲。一行が天竺を目指す道中で神奈川県に迷い込み、県内各地域の伝説や昔話の世界を旅する冒険譚。長塚圭史が上演台本・演出・出演を務める。
※5
公演関係者に新型コロナの陽性が確認されたため、ツアー公演の一部が中止となった。
新ロイヤル大衆舎×KAAT 『王将』-三部作- 公式サイト
「冒険者たち ~JOURNEY TO THE WEST~」公式サイト
芸術監督就任2年目となる2022年度
メインシーズンのタイトルは「忘」。
ラインアップはこちら
https://www.kaat.jp/news_detail/1925
私たちは猛スピードで進む現在に立ち、大切なことをどんどん忘れていきます。
人間は忘れる生き物。
忘れるという罪を背負っているのかもしれません。
時に自ら目を逸らし、積極的に忘れることもあります。
忘れることは力に変わります。
忘れない。忘れられないこともあります。
数々の災害、コロナ禍の中で、人々はどうたくましく歩んできたのか。
広大な記憶の荒野に立ち、私たちは今、何を思うのか。

長塚圭史[ながつか・けいし]
劇作家・演出家・俳優。1975年生まれ。早稲田大学在学中に「阿佐ヶ谷スパイダース」を結成し2018年に劇団化。2011年ソロプロジェクト「葛河思潮社」を、2017年には「新ロイヤル大衆舎」を始動。2019年4月よりKAAT神奈川芸術劇場芸術参与。2021年4月、KAAT神奈川芸術劇場芸術監督に就任。